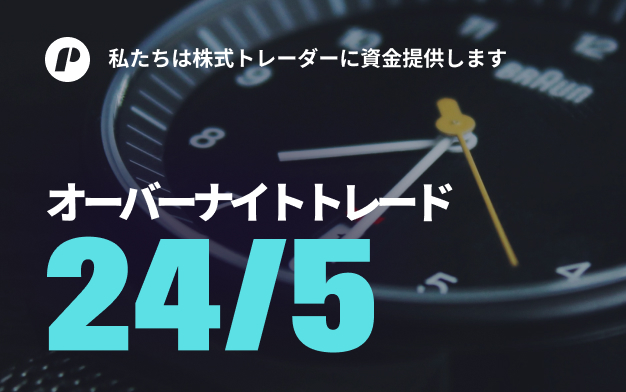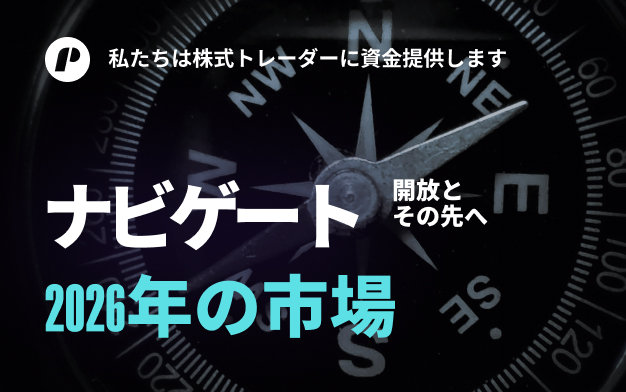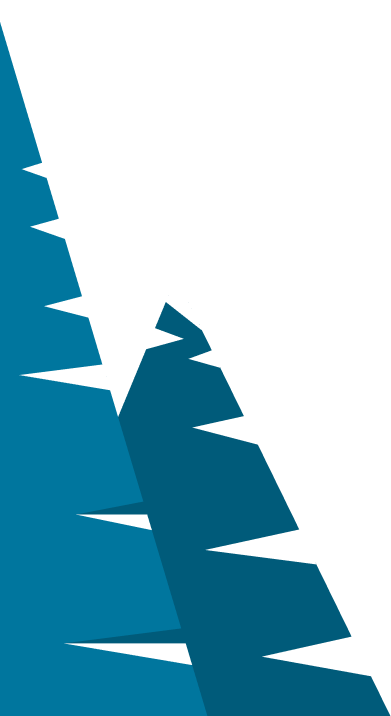空っぽの約束とまやかし。金融市場という混乱した世界の中で、多くのトレーダーが本当に機能する取引方法を必死に探しています。 世の中には多くのアイデアがありますが、その中でICTは人気がありながらも時に議論を呼ぶ手法です。「スマートマネー」がいつも自分のストップロスを狙ってくるように感じたことがあるなら、それはあなただけではありません。そして、多くのトレーダーが注目しているのがICTコンセプトなのです。では、ICTトレーディングとは何か?それは「The Inner Circle Trader」として知られるマイケル・ハドレストン(Michael J. Huddleston)によって作られた、特定で包括的なトレーディング手法です。大手機関の取引方法を分析し、価格アクションに密接に注目することに重点を置いています。
その主な目的は?市場の中でお金がどう動くか(流動性)、市場構造、そして大口投資家の典型的な取引パターンや、時には操作すらも視野に入れながら、高勝率のトレードを見つけることです。一般的なトレンド系やモメンタム系のインジケーターには頼らず、あくまで価格そのものから導かれる情報に基づいています。
ポイントまとめ
-
- ICTの基本概念を理解する
- ICTとは何の略か?
- ICTの中身とは?
- ICTとリテールトレーディングの違いとは?
- ICTトレーディングにおける流動性とは?
- ICTの最適エントリーポイントとは?
- ICTでインジケーターはどう使うの?
- ICTトレーディングで最適な時間足は?
ICTの基本概念を理解する
ICTトレーディングのコンセプトは、「スマートマネー」と呼ばれる大手機関投資家が何を計画しているかを、価格の動きを詳細に観察することで理解することにあります。これらの大口投資家は非常に大きな取引量を扱うため、注文をうまく成立させるために価格をある程度動かす必要があるのです。
それを理解し、彼らと同じ方向に取引するために、ICTは一連の重要な考え方を使います。市場構造を見て全体像をつかみ、機関投資家が注文を入れていそうな重要なポイント(ICTでいうオーダーブロック)を探し、価格があまり取引されずに素早く動いた領域(フェアバリューギャップなど)を確認し、今後価格がどこへ向かうのかを予測します。こういった技術を習得することで、トレーダーは機関投資家の動きを理解し、より賢明なトレード判断ができるようになります。
ICTとは何の略?—ICTコンセプトの基礎を探る
で、ICTって? これは「Inner Circle Trader(インナーサークルトレーダー)」の略なんです。ちょっとカッコいい響きですよね?マイケル・ハドレストンが提唱したこの考え方は、市場を「内部者」のような目線で見る方法として知られています。「インナーサークル」という言葉には、大手機関が裏で何をしているのかを見ることができる、というニュアンスが込められていて、一般的なトレーダーには見えない部分まで見えるようになるという意味があります。ハドレストンはこの名前を通じて、機関投資家のように市場を見る方法を人々に教えたかったのです。
彼はICTの原則を学べば、価格が動く本当の理由を理解できると考えました。そして今では、「ICTトレーディング」という言葉はこのスタイルの代名詞になっており、「スマートマネー」が何をしているかを的確に読み取り、それに基づいて高確率のトレードを行う、まさに“内部情報”に基づいた戦略として定着しています。すべてはICTコンセプトを理解することから始まるのです。つまり、トレーディングの世界で「ICT」と言えば、マイケル・ハドレストン(Michael J. Huddleston)の「Inner Circle Trader」手法とその中核をなすICTコンセプトを指しているのです。
ICTには何が含まれているのか?
では、ICTのツールボックスには実際に何が入っているのでしょうか?それは、市場を深く理解するための一連の関連した考え方やツール、テクニックの集まりです。特に重視されるのが市場構造の理解で、主な高値や安値を見極めて市場の方向性を予測することです。さらに、流動性プールという概念があります。これは、ストップロスや利益確定注文が集中しているゾーンのことで、大手機関はこれらを狙って注文を成立させることがあります。オーダーブロックも重要で、これは大口投資家が注文を出した可能性の高い価格帯であり、今後のサポートやレジスタンスとして機能します。フェアバリューギャップ(FVG)は、価格に生じた不均衡のことで、後に埋められる可能性があります。
ICTでは、価格が一度動いた後の押し目(戻り)で良いエントリーポイントを見つける「最適トレードエントリー(OTE)」という手法を使います。これはフィボナッチ・レベルを活用した方法です。また、”キルゾーン”と呼ばれる、取引が活発になる特定の時間帯にも注目します。ICTではRSIのようなインジケーターも、特定の方法で使うことがあります。さらに、アジア、ロンドン、ニューヨークといった異なる市場時間帯が価格にどう影響するかも分析対象です。こうしたアイデアすべてが組み合わさり、機関投資家のような視点で市場を見る方法を構築しています。
ICTとリテールトレードの違いとは?
さて、ICTのトレーディング手法は、一般的なリテールトレードとは大きく異なります。その違いを見てみましょう:
- 市場の見方:リテールトレーダーはインジケーターや単純なチャートパターンを使い、市場に一定のルールがあると考えがちです。一方ICTでは、大口の機関投資家(スマートマネー)が何をしているかを読み取ることに注力し、価格、マーケット構造、資金の流れ(流動性)に注目します。
- 使うツール:リテールはたくさんのインジケーターに頼る傾向があります。ICTはほとんどの場合、プライスアクション(価格の動き)を重視し、あまり多くのインジケーターは使用しません。
- 注目するチャート:リテールトレーダーは1つの時間足に固執しがちです。ICTでは複数の時間足を見て大局を掴み、その上でエントリーポイントを絞り込みます。
- 市場を動かす要因の捉え方:リテールでは単純に需給やインジケーターによるシグナルと考える人も多いです。ICTでは、大きな価格の動きは機関投資家が大量の注文を入れる必要があるときに起こると考えます。ときには他のトレーダーを騙したり、流動性を得るためにわざと小さな動きを起こすこともあるのです。
- 重視する考え方:リテールではサポート、レジスタンス、トレンドがよく語られます。ICTではマーケット構造の変化、オーダーブロック、フェアバリューギャップ、流動性、キルゾーン、マーケットメーカーの動きなどに焦点を当てます。
ICTトレーディングにおける「流動性」とは?—ICTの中核概念
ICTにおいて流動性とは、特定の価格帯に大量の買い注文や売り注文(ストップロス、利確、指値など)が集まっている場所を指します。これは非常に重要です。なぜなら、大手機関は莫大な取引量を持っており、その注文を市場に影響を与えずに成立させるには、こうした注文の集まった場所を狙う必要があるからです。ICTでは、機関投資家が意図的に価格をストップロスが集中する場所に動かし、それを引き金に流動性を確保すると考えます。ICTトレーダーは、価格の高値・安値付近に流動性があると見ており、それが次の価格の動きのヒントになると考えています。
ICTの最適トレードエントリー(OTE)を理解する
OTEとは、価格が大きく動いた後の戻りで、最適なエントリーポイントを探す、ICT独自の精密な手法です。この「スイートスポット」は、フィボナッチ・リトレースメントの62%〜79%の間にあることが多いです。このエリアは、「大口」が一度他のトレーダーを振るい落としてから、ポジションを追加する場所とも考えられています。ただし、単にOTEゾーンに入ったからといってすぐにエントリーするわけではありません。ICTトレーダーは、他の要素(コンフルエンス)—たとえばオーダーブロックやフェアバリューギャップなどとの一致—を確認します。価格がこのゾーンに入り、元の方向に動きそうなときがエントリーチャンスです。OTEは、良い価格でエントリーできるため、リスクとリワードの面で優れています。高確率なセットアップを狙うICT戦略において、中心的な要素の一つです。
ICTの最適トレードエントリーとは?
ICTの最適トレードエントリーとは、ICT OTE戦略の正式名称です。価格が戻したときに、フィボナッチ・レベルを使ってベストなエントリーポイントを探す手法です。
ICT OTE戦略とは?
ICT OTE戦略とは、「最適トレードエントリー」テクニックを使うことを意味します。 OTEは「Optimal Trade Entry(最適トレードエントリー)」の略で、フィボナッチの62%〜79%ゾーンを見つけ、その他の根拠と組み合わせて高確率なトレードを狙います。
ICTトレーディングでのインジケーターの使い方
ICTトレーディングを始めると、最も大切なのは「プライスアクション」と機関投資家の動きを理解することだと気づくでしょう。 他の多くの手法のようにインジケーターだらけにはせず、ICTでは基本的にシンプルに保ちます。インジケーターはメインではなく、あくまで補助として使います。例えば、相対力指数(RSI)は、価格が重要なICTレベルにあるときにダイバージェンスを見つけるために使うことがあります。 専用の「ICTインジケーター」があるわけではなく、ICTでは一般的なインジケーターを、価格やマーケット構造、機関投資家の行動といった考え方に沿って活用する方法を教えてくれます。
ICTコンセプトにおけるインジケーターの役割とは?
ICTでは、インジケーターは主に、プライスアクション、マーケット構造、流動性から導き出したトレードアイデアを裏付ける「確認要素」として使われます。 インジケーターだけでトレードするのではなく、自信を深めるための補助として機能します。
ICTではRSIのような一般的インジケーターをどう見ている?
ICTでは、RSIのような一般的インジケーターを、普通とは違った使い方をすることがあります。 単に「買われすぎ」「売られすぎ」と判断するのではなく、たとえば価格が重要なICTレベルにあるときに、RSIがあるレベルを超えない、またはダイバージェンスを示しているかなどを見ます。
ICT専用のインジケーターはある?
いいえ、ICT専用のインジケーターというのは特に存在しません。 ICTメソッドでは、既存のインジケーターを「ICTの核となる市場理解」に沿って使う方法を教えているのです。常に主軸となるのは「価格を理解すること」と「大口投資家が何をしているかを読むこと」です。
ICTトレーディングに最適な時間足とは?ICTコンセプトの応用
経験豊富なトレーダーなら、長期と短期で市場の見え方が変わることをよく知っています。ICTでは、「この時間足が一番いい」とは決めつけません。 むしろ、いろんな角度から市場を見て全体像を把握することが大切とされています。市場構造、大口資金(流動性)、機関投資家の動きといったICTの核となる考え方は、どの時間足にも現れます。だから、あなたにとっての「ベスト」は、どんなスタイルでトレードしたいか、目標は何か、どれくらいの時間を割けるかによって変わるんです。
大局観をつかむ:マーケットバイアスと主要レベル(日足・週足・月足)
これらはまるで地図のような存在です。 ICTトレーダーはまずここから見て、全体として市場がどの方向に向かっているのかを確認します。機関投資家が注目しているであろう高値や安値、または大口注文が入っていそうなオーダーブロックや、長期的なフェアバリューギャップなどを探します。こうした情報は、どこがサポート・レジスタンスになるか、どこを目指して動くのかといった背景を与えてくれます。
詳細を見極める:構造の洗練とスイートスポットの発見(4時間・2時間・1時間)
こういった中期の時間足を見れば、市場の動きの詳細がより明確に見えてきます。 方向転換や重要な価格帯のブレイクなどがよりはっきりと確認できます。ICTトレーダーは、これらの時間足を使ってスイートスポット、つまり、上位足で確認した動きと一致する小さなオーダーブロックやフェアバリューギャップなどを探します。こうした場所はエントリーを検討するのに最適なポイントです。
細かい部分まで見ていく:エントリータイミングを測る(15分足・5分足・1分足)
これらの時間足は、エントリーのタイミングを正確に捉えるために使います。 上位足で注目のエリアを見つけたら、ここでズームインしてベストなタイミングを探します。 ICTトレーダーは、特定の価格パターンや、取引量が最も活発になる「キルゾーン」内での急激な動きを観察することがあります。 スキャルピングなど、素早いトレードが好みの人は、この時間足をよく使います。
すべてをまとめる:あなたのスタイルと市場のリズム
ICTでは、特に「キルゾーン」と呼ばれる時間帯の重要性も重視します。でも実際には、どの時間足をメインに使うかはあなたのトレードスタイル次第です ― 数分、数時間、数日持つかで変わります。 ICTの良いところは、どんなスタイルにも応用できる点です。ただし、まずは大局(ビッグピクチャー)から始めて、そこから徐々に絞り込んでいくのが基本です。

ICTトレーディングにおける「ディスプレイスメント(価格の急変動)」とは
ICTでの「ディスプレイスメント」とは、価格が急激かつ力強く上下に動くことを指します。 チャート上では、長いローソク足が連続して同じ方向に伸び、ヒゲがほとんどないような形で表れます。ICTによると、ディスプレイスメントには2つの大事な要素があります:ひとつは、買いまたは売りの勢いが一気に強くなったこと(特に流動性のあるゾーンでよく起きる)、もうひとつは、この動きが「マーケット構造の変化(MSS)」と「フェアバリューギャップ(FVG)」をほぼ確実に生み出すということです。

ICTトレーディングにおける「マーケット構造の変化(MSS)」とは
ICTでの「マーケット構造の変化(Market Structure Shift:MSS)」とは、現在のトレンドが崩れる瞬間を指します。 上昇トレンド(ブル)なら、高値と安値が切り上がっていたのに、安値を更新する「ロー・ロー」が出現する時です。下降トレンド(ベア)なら、安値と高値が切り下がっていたのに、高値を更新する「ハイ・ハイ」が出る瞬間。このようなMSSは、トレンド転換の初期サインとしてICTトレーダーに重視され、他の要素(構造、流動性、FVGなど)と組み合わせて、トレード開始の手がかりとして使われます。
ICTトレーディングにおける「誘因(Inducement)」とは:ICT概念の適用
誘因とは、大きなトレンドの中で小さな逆トレンドの端で起きる価格の動きです。 ICTトレーダーは、これが「スマートマネー」が下位時間足でストップロスを狙っている結果だと考えています。 この考え方では、価格が誘因レベルに到達して追加の資金(流動性)を集めた後、再び方向を転換し、主要なトレンドに従って進むと予測されます。 ICTトレーダーは、誘因の後、価格が大きな時間足トレンドに沿って動くと信じて、トレードを計画します。
ICTトレーディングにおける「フェアバリューギャップ(FVG)」とは:ICT概念の適用
大きな流動性レベルが突破され、トレンドが変わると、チャートに「ギャップ」のようなものが現れることがあります。 ICTトレーダーはこれを「フェアバリューギャップ(FVG)」と呼びます。 通常、これには3本のローソク足が連なっており、その中央のローソク足が長く、隣接するローソク足のヒゲとの間にギャップがあるのが特徴です。 これらのフェアバリューギャップは後で埋められることが多く、ICTトレーダーはトレードの設定時にこの考え方を活用します。
ICTトレーディングにおける「バランスドプライスレンジ(BPR)」とは
バランスドプライスレンジ(BPR)とは、2つの反対方向のディスプレイスメント(価格の急変動)が近接しているときに発生し、2つのフェアバリューギャップを形成する現象です。 価格がBPR内にあると、価格は上下に動きながら、両方のフェアバリューギャップを埋めようとします。 ICTトレーダーは、この上下動を利用してトレードし、BPRを突破した後は元のトレンドに従って価格が動き続けると考えています。
ICT概念の要約とポイント
多くのトレーダーは金融市場が混乱していると感じており、理解しやすい方法を常に探しています。ICT(Inner Circle Trader)は、マイケル・ハドレストンによって作られた、金融市場を理解するための包括的なトレーディングプログラムです。 ICTは、通常のインジケーターを使うのではなく、大きな機関(「スマートマネー」)が実際に行っていることに注目します。 主な焦点は、価格自体の動き、市場の構造、そして流動性(買いと売りの注文が集まる場所)です。
大きな機関は、通常、自分たちの大規模な取引を実行するために必要な買いと売りの注文を集めるために市場を少し動かすことが多いです。 ICTは、トレーダーにこれらの動きを見つけて、「スマートマネー」と一緒に取引する方法を教えたいと考えています。 これには、オーダーブロックやフェアバリューギャップの理解、最適な取引エントリー(OTE)を使って良いエントリーポイントを見つけることが含まれます。
ICTはインジケーターに重点を置いていませんが、RSIなどの一般的なインジケーターを使って、見ているものを再確認する方法を示します。 ICTの大きな部分は、市場をさまざまな時間足で見ることです – 最初は大局を把握し、その後、エントリーのベストな場所を見つけるためにズームインします。
この記事が気に入ったら、ぜひシェアして下さい!